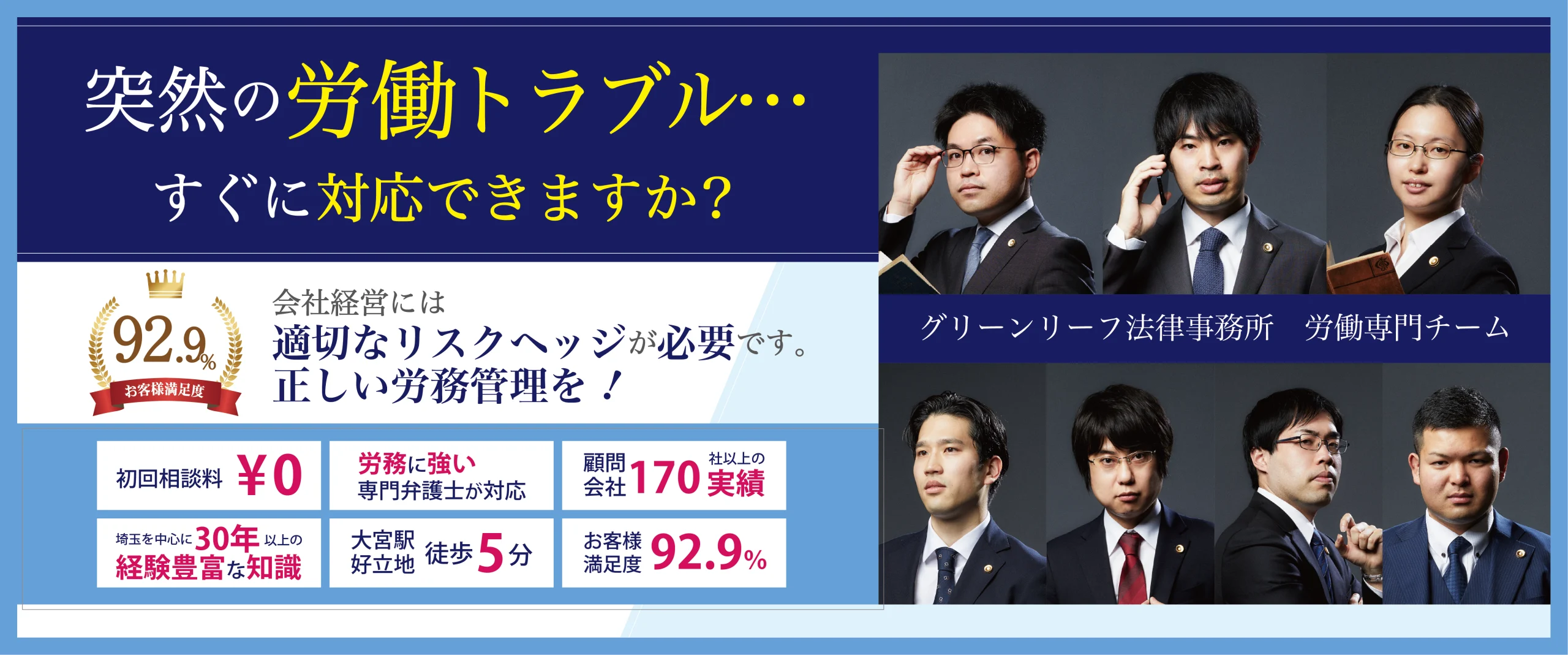入社時の研修、職種別研修など、企業には様々な研修がありますが、「研修に参加した従業員に対し、通常の業務と同様に給料(賃金)を支払う必要があるのか?」といった疑問を持たれる企業もいらっしゃるかと思います。
本ページは、従業員への研修に給料や残業代は発生するのか否か、そして研修参加の強制の違法性の有無について専門家が解説するページとなっております。
そもそも研修は「労働時間」に当たるのか?基礎知識

労働基準法11条にでは、「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定められております。
つまり、従業員が「労働」をしていた場合には「賃金」が発生いたします。
研修に参加する時間が「労働」時間に当たるかどうかについて、裁判例上、「労働者が使用者の指揮命令下で働く時間」が労働時間に当たるとされております。
したがって、研修参加が使用者の指示によるものである場合は、労働時間に該当すると可能性が高いと考えられますので、給料(賃金)が発生すると考えられます。
研修参加を強制することは可能なのか?

使用者が労働者に対し、業務命令の一環として研修への参加を指示(強制)できることがあります。
以下では、研修参加を強制できる場合・できない場合についてそれぞれ詳しく解説いたします。
1 研修参加を強制できる場合
研修への参加が業務上必要かつ合理的であれば、労働契約に基づく業務命令の一環として、労働者を強制的に研修へ参加させることができると考えられます。
例えば、初任者研修・アルバイト研修・コンプライアンス研修・管理職研修については参加強制できると考えられます。
2 研修参加を強制できない場合
研修の内容が業務上の必要性または合理性を欠く場合は、労働者を強制的に研修へ参加させることはできないと考えられます。
例えば、業務と関連性がない内容の研修・不当な長時間にわたって労働者を拘束する研修
・労働者の人格権を侵害するような内容の研修などについては参加強制できないと考えられます。
研修中の給料の取り扱いについて

研修時間が労働時間に当たる場合、通常の業務と同様に給料を支払う必要があります。
また、強制参加の場合に限らず、任意参加による研修であっても、給料が発生すると考えられますのでご注意ください。
研修参加が強制か任意であるかは、実質的な観点から判断されます。
名目上は任意参加であっても、事実上強制と評価すべき場合には、使用者の指揮命令下で行われるものとして給料が発生しますのでご注意ください。
例えば、業務上必須の情報を学ぶための研修・ほぼ全員の労働者が参加している研修・参加しなければ待遇に関して不利益を受ける可能性が高い研修などは、名目上は人に参加であっても給料が発生すると考えられます。
研修への参加を拒否された場合の対処法について
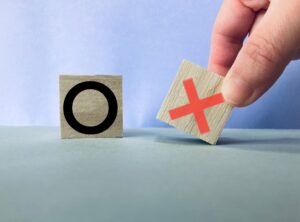
従業員が研修への参加を拒否した場合には、使用者は労働者に対して懲戒処分を行うことが考えられます。
もっとも、懲戒処分を行う際には、懲戒権の濫用に当たらないように注意する必要があります。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない懲戒処分は無効でありますので(労働契約法第15条)、場合によっては従業員から損害賠償請求を受ける可能性もございますのでご注意ください。
断固として研修参加を拒否するといった態様をとってきた場合、戒告などの軽い懲戒処分から行い、改善指導の効果がない場合には重い懲戒処分へ段階的に移行するのがよいと考えられます。
研修時間に対する給料を支払わなかった場合、どうなる?

研修時間に対して支払うべき給料を支払わなかった場合、以下のような事態が発生する場合がありますのでご注意ください。
1 労働基準監督官から是正勧告を受ける
従業員の申告などをきっかけに、労働基準法違反が疑われる事業場に対し、労働基準監督官による臨検(立ち入り調査)が行われることがあります。
立ち入り検査の結果、労働基準法違反の事実が判明した場合は、監督官から是正勧告を受けます。
是正勧告を受けた使用者は、一定期間内に違反状態を是正して、労働基準監督署へ報告する必要があります。
2 送検されると事業者名が公表される
給料の未払いは犯罪に当たり(労働基準法第24条、第120条第1号、第121条)、給料の未払いが大規模である場合や、労働基準監督官の是正監督に繰り返し従わなかった場合などには、労働基準監督官が検察官に対して事件を送致する可能性が高くなります。
この場合、都道府県労働局のウェブサイトで事業者名が公表されたり、行為者・法人の双方に対して「30万円以下の罰金」を科されたりするおそれがあります。
まとめ

以上、研修参加に対する給料が発生する場合、研修への参加強制の可否などについて解説いたしました。
研修は社員育成のために重要なものでありますので、研修時間が労働時間に該当する場合には、しっかり給料を支払っていただく必要がございます。
また、研修参加を拒む従業員に対する対処についても慎重な対処が求められますのでご注意ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。