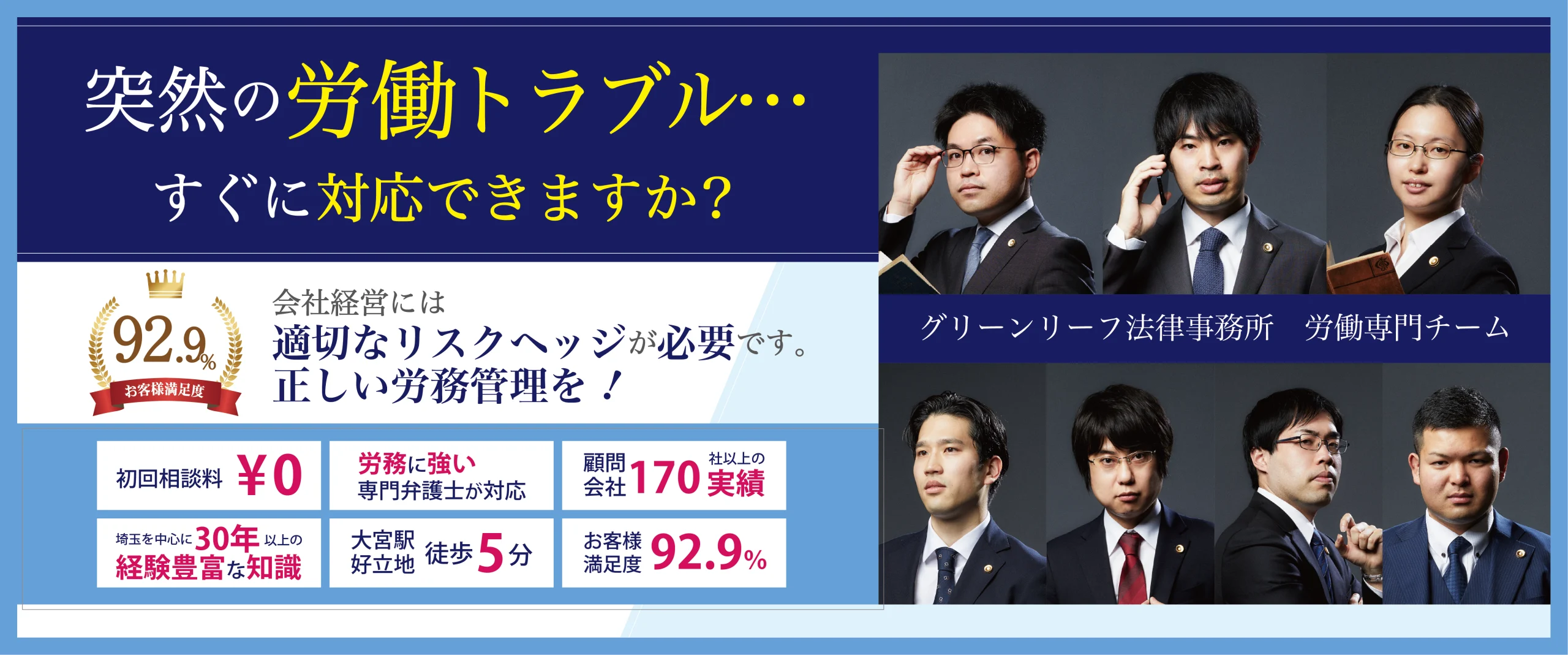2022年(令和4年)4月1日から、中小企業にも職場のパワーハラスメント対策を義務づけられています。その義務の中では、ハラスメントにかかる相談の申し出に対する企業側の対応についても触れられており、厚生労働省の「パワハラ防止指針」でも、「事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること」として企業側に調査すべき義務があるとされているのです。そこで、今回はこのハラスメント被害相談があった場合の調査義務について掘り下げていきます。
企業が負うハラスメント被害申告に対する調査義務

調査義務とは
厚生労働省が定める「パワハラ防止指針」によれば、従業員からハラスメントに係る相談の申出があったときは、企業は「事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する」べき義務を負っているとされています。
具体的な取り組みとしては、
①相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談者及び行為者の双方から事実関係を確認すること。その際、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止め等その認識にも適切に配慮すること。また、相談者と行為者の間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。
②事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合等において、労働施策総合推進法第30条の6、男女雇用機会均等法第18条又は育児・介護休業法第52条の5に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねることも考えられること。
などとしています。
このとおり、企業にはハラスメントについての調査義務があり、調査義務違反は損害賠償請求の対象にもなりえるのです。迅速な対応をするためには、その対応のための段取りを決めておかねばなりませんので、後記のとおり、実際の相談事例が生じる前に、マニュアルを作成しておく、ということが重要です。
調査義務違反に対し、賠償義務が認められているケースもある

東京高等裁判所平成29年10月26日判決では、パワハラの訴えがあったのに事実関係の調査をせず、ハラスメント被害者が自殺に至ったという事案に対し、
「上司は…パワハラの訴えを受けたのであるから,パワハラの有無について事実関係を調査確認し,人事管理上の適切な措置を講じる義務があるにもかかわらず,事実確認をせず,かえって,職場における問題解決を拒否するかのような態度を示し,…パワハラの訴えを放置し適切な対応をとらなかった」
として、として、約1000万円の損害賠償が命じられています。
また横浜地方裁判所平成16年7月8日判決では、セクハラの訴えがあったのに対して、加害者をかばう発言を繰り返して適切な措置をとらなかったという事案に対し、
「課長は、…事情聴取等からセクシュアルハラスメントがあったことを認識していたにもかかわらず、原告(※ハラスメント被害者)から事情を聴き取ったりすることもなく、…客観的な証拠である本件写真が存在していることを知りながら、これを収集せず、原告の求めで面談した際にも、原告が異動を希望していると思い込み…待つよう述べただけで、原告が…係長の行為によって極めて大きな苦痛を受けており、また職場で蚊帳の外に置かれているとして救済を求めたのに対しても、今の文書法制係が原告には荷が重すぎたのかもしれないなどと原告の責任であるかのような発言をし、また全体的に係長をかばう発言を繰り返し、結局原告に対し何らの措置をとることなく、また係長についても何らの処置を検討することもなかったものである。結局、課長は、問題解決にとって特に重要な事実の調査・確定を十分行わず、当時同課長が把握していた事実によっても当然検討すべきであると考えられた被害者である原告の保護や加害者である係長に対する制裁のいずれの点についても、何もしなかったと評するほかはない。…係長の言動は、原告に対する重大な人権侵害と評価すべきものである。このことを前提に考えると、課長の不作為は、その権限及び職責を定めた本件基本方針及び本件要綱の趣旨・目的や、その権限・職責の性質等に照らし、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くものというべきである。よって、同課長の権限不行使は、原告との関係において…違法というべきである。」
として、88万円の損害賠償が命じられた事例です。
そもそも調査を実施ないこと自体が義務違反になることは当然のことですが、調査していても調査方法・調査対応が不適切であるとして、損害賠償が命じられることもあります。
あるべき調査体制について

調査対応者の構成
まず、調査を実施する者としては、複数名で構成するのが良いと考えられます。
ハラスメント相談窓口の担当者は、相談内容を調査担当の部署に引継ぎ、調査は、そちらにゆだねることが一般的なようです。
調査担当部署は、被害者、加害者、関係する第三者らに対しヒアリングなどによる調査を行ったうえで、今後の人事的措置及びハラスメントが認められる場合の懲戒処分の要否及びそのレベルのいずれに対しても判断していきます。
これらの判断内容を踏まえると、人事的な側面・法務的な側面の両面から複数名で構成することが良いと考えられます。
また、相談担当・調査担当は、担当者の性別にも配慮をする必要があると考えられます。女性のみ・男性のみといった調査や判断にゆだねると、偏った見方になってしまう可能性もありますので、可能な限り公平・公正な構成にしていきます。
調査の実施方法

(1)被害者からの聴き取り調査
まず、被害者からの聴き取りにあたっては、まず、被害者の精神状態に配慮し、被害者の訴えを受け止めることが重要です。
聴き取りの際に「被害者にも落ち度があったのではないか」といった二次的被害を生じさせることがないよう注意を払う必要があります。
まずは被害者の訴えをそのまま受け止め、被害者の主張をその場で判断しないようにしましょう。
また、可能な限り聴き取りに誤りがないよう、聞き取った内容を被害者に確認することも重要でしょう。
聴き取りにおいて、客観的な資料、たとえばSMS・メールなどのやり取り・写真などもあるのであれば、提出をしてもらいましょう。
(2)加害者からの聴き取り調査
加害者とされる者からの聴き取りは、前提として被害者にも意思確認をして行いましょう。被害者の中には、「単に被害相談をしたかっただけで、調査等は望まない」、「加害者に自分の被害申告を絶対に知られたくない」という方もいらっしゃいます。
もちろん、ハラスメントに対する対応は会社の責務ではありますが、被害者の意思は尊重しなければなりませんので、そのような義務があること、会社としては被害申告をした方に不利益が生じないよう対応する義務もあることを良く説明し、調査を進めることに承諾を得ておきます。
上記を踏まえ、加害者とされる側から聞き取りをする場合は、ハラスメントの被害内容について、事実かどうかなど確認していきます。被害内容そのものだけではなく、その周辺事項、たとえば加害者とされる側と被害者との人間関係や、問題があったとされる言動に至った経緯等も、聴き取ることによって判断の参考になることがあります。
加害者とされる側からの聞き取り内容についても、被害者と同様、誤りがないかを確認します。
(3)第三者からの聴き取り調査
当事者である被害者側・加害者側だけではなく、中立的な第三者たる目撃者や関係者がいる場合、その人たちにも聴き取り調査をします。
ハラスメント加害者による被害は、1度に限られることは稀で、同様の被害が以前にもあった、ということもあるので、同じような事案がなかったかという過去の調査も、ハラスメントの有無について被害者側・加害者側の言い分が食い違う場合に参考になります。
第三者からも聴き取りをする場合、プライバシーや思い込みに配慮せねばなりません。そもそも被害者側の訴えがあったことをそのまま明らかにしてしまうと、予断が入ってしまう可能性もあるからです。
(4)その他の方法
上記のような思い込み・予断に配慮した調査方法として、「アンケート」があります。
例えば、社内のハラスメントの有無について、匿名で回答できるアンケート調査を部署内の従業員全員に行うなどして、今回被害を訴えている方の問題にとらわれず、同様のハラスメント被害を受けている人がいないかを調べるのが望ましい場合もあります。
信用性のある調査実施のために

ハラスメントの加害者が、社内で重要人物である場合など、調査結果が聴き取った第三者らと加害者とされる方との人間関係に影響されないとも限りません。そのような聴き取りの実効性を損なうようなことがないように、幅広い範囲に事情聴取する・聴き取った対象に対し調査を受けたことによる報復人事などをしないことを約束させ、公正さを確保することも重要です。
調査終了後の対応
事実確認の結果(双方主張の食い違い)
調査の結果、両者の主張が食い違い、どちらの言い分が正しいか分からない場合はどうしたえら良いでしょうか。判断のポイントとしては、以下の点が挙げられます。
①被害者側・加害者側の主張と、客観的な資料との整合性
②被害者側・加害者側の主張の変遷に不自然な点はないか
③被害者側のハラスメント被害を主張した契機・虚偽を述べる動機の有無
②同様の被害事例はないか
その他
以上がハラスメント被害の申告があった場合の調査のポイントですが、このような調査の段取りは、なかなか一朝一夕には整理できないものです。いつ相談があっても良いように、あらかじめ調査・処分のマニュアルを作成しておき、会社としてハラスメントを放置しないこと、厳正に対応する姿勢を表明することで、既に生じてしまった被害者に安心感を与え、さらに将来的なハラスメント行為の予防にも繋がると考えられます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。