
セクシャルハラスメントの問題は、何がセクハラか、ということを知らなければ自らが加害者になってしまうかもしれません。また、その定義について知っていても対応を誤れば加害者になってしまうということがあります。「自分だけは大丈夫」と思ってしまったり、「このくらいなら大丈夫」と思って加害に及んでしまうだけではなく、被害者から相談を受けた人が、二次被害を生んでしまうケースも近年問題になっています。
この記事では、まずはセクハラが法的にどのようなものなのかを知り、自分がハラスメントを「しない」、他の人にハラスメントを「させない」という職場環境を作るため、事前の予防や事後の対処のためのポイントを弁護士が解説します。
企業が取り組むべきセクハラ対応策 実践にあたり注意すべきポイント
日本で「ハラスメント」という言葉が最初に話題になったのは、平成元年ころ、謝った情報を基に「異性関係が派手だ」などと社内でほかの社員より噂をながされたことが問題であるとして裁判になった「福岡セクシュアル・ハラスメント事件」だといわれているようです。
その事件後、30年以上が経過し、セクハラという概念は広く人々に認知されるようになりました。しかし、その後もセクハラやハラスメントという概念は広がりを見せ、近年では「SOGIハラスメント」という性的指向・性自認に関する差別や、いやがらせなども問題視されるようになりました。
まずはセクハラという概念について、正しい知識を知り、「ハラスメントをしない」という最低限のラインから、さらに進んでセクハラをしない・させないための環境づくり・予防策・事後措置について、企業がなすべき対策について解説していきたいと思います。
セクシャルハラスメントとは何か?その定義とは

法律上の定義
セクハラについては、男女雇用機会均等法で規定されており、
「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」
とされています。
この法律上の文言からも明らかなように、被害者は男性か女性かを問いませんし、職場での従業員の上下関係も不問となっています。
つまり、必ずしもセクハラの被害者は女性でなければならないわけでもないし、加害者が男性に限られるわけでもありません。同性間でセクハラ行為が生じることはあり得ますし、上司から部下になされる、というものに限らないのです。
セクハラの態様類型
これまで、セクハラの態様としては、以下の2つの類型があるとされてきました。
1つは、対価型セクハラといわれる、「職場において行われる労働者の意に反する性的な言動(発言や行動)への対応により労働者が不利益を受けること」という形です。
具体的には、
・上司が部下をデートに誘ったが無視されたため、その部下のボーナス査定をゼロとしたり、解雇を匂わせたりした
・社長が契約社員に性的関係を求めたが拒まれたため、次回の契約を打ち切り にした
などといった態様がこれに当たります。
もう一つの類型としては、環境型セクハラという「職場における性的な言動によって職場環境が害されること」があります。
こちらの具体例としては、
・性的な冗談を言う
・性的事実に関する質問をする
・電話やメールで食事やデートに誘う
・身体に不必要に接触する
・性的な話をして盛り上がる
ほかにも、性差別意識に基づく発言として、
・「女は結婚してすぐ退職する者が多い」
・「男なんだから、結果を出せ」
・女性だからとお茶汲みをさせたり、
・飲み会でお酌を強要する
などといったことも、この類型に当たります。
誰を判断基準とするか
セクハラの該当性は、あくまでも受け手を基準に考えます。受け手の感じ方も千差万別かもしれませんが、裁判所の判断としては、平均的な男性労働者・女性労働者の感じ方を基準としています。
ただ、その感じ方の基準というのは決して普遍的なものではありません。つまり、以前は問題視されなかった言動が、時代や社会通念の変遷とともにセクハラに該当するようになるかもしれないということです。
「自分も昔会社の上司や同僚などに言われていたことだから、この行為や発言はセクハラにはならないだろう」というのは大きな間違いで、言葉や態度というのは、常に受け取る側に与える意味も変わってくることがあります。
たとえば、昭和の時代には、中年の女性に対し、「おばさん」などと呼ぶことは当たり前であったかもしれません。しかし、裁判例のなかでは、「おばさん」といった発言や、「おばん」「くそばばあ」と呼んだことなどを、「人格権を侵害する不法行為」 と認定し、セクハラ該当性を認めた事例もあります。
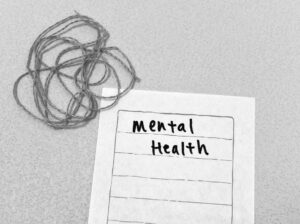
セクハラによってどのような責任が生じるか
そもそもセクハラは何故許されないのでしょうか。これを考えるには、セクハラが生み出す悪影響について考得なければなりません。
セクハラが被害者や会社に与える悪影響は様々あります。典型的なものとして以下のものを紹介します。
(1)被害者に対する影響
・不快感、不安、恐怖等に悩まされる
・自分に対する自信がなくなる
・仕事上で能力が発揮できなくなる
(2)他の従業員への影響
・次は自分が言われる(される)かもしれないという不安を感じる
・あの人が許されるなら自分も大丈夫だと思う…結果として職場でセクハラが横行してしまう
・職場全体のモチベーションが下がる
(3)会社への影響
・加害者とともに被害者に対する賠償責任を負う可能性がある
・企業名の公表により、社会的信用を失う
・職場環境の悪化により、生産性が上がらなくなる
以上のとおり、職場内でセクハラが発生しないよう一緒に働く全員がセクハラに対する正しい知識を持ち、その防止を実践していくことが極めて重要です。セクハラは、加害者・被害者の2者間の問題ではなく、会社も巻き込んだ大きな問題だという認識を持つ必要があります。
SOGIハラとは何か?
また、近年では新たな問題意識として、「SOGIハラ」という概念も知っておかなければなりません。
「SOGI(ソジ)」とは「Sexual Orientation(性的指向) and Gender Identity(性自認)」の頭文字からとったもので、「SOGIハラ」は性的指向や性自認による差別やいやがらせのことを指します。
令和元年(2019年)に厚生労働省の労働政策審議会にて出されたパワーハラスメント防止対策を義務付ける指針があります。
令和2年(2020年)以降、改正労働施策総合推進法(通称 パワハラ防止法)でSOGIハラ、アウティング(本人の了承を得ずに、その者の性的指向や性自認を暴露すること)を含めたパワーハラスメントの防止対策が各企業にも「措置義務」として課されており、対策を怠った場合には労働局による助言・指導・勧告等が行われることになっていますから、注意が必要です。
特に、SOGIハラの難しい点は、このようなハラスメントがあったとしても、その被害者が企業の窓口などに相談をしたくても、それを躊躇してしまうことです。なぜならば、被害者はSOGIハラについて相談しようとすれば、相談先に対し、自らの性的指向や性自認を開示せざるを得ません。そうすると、なかなか相談を積極的にできない被害者も出てきてしまうと考えられます。
相談がないからといって、このようなハラスメントが存在しないということにはならないことは、企業としても常に意識をしていなければいけません。

セクハラ被害・加害の本質とは
セクハラの被害発生を防止するためには、その本質を理解しなければなりません。
セクハラ加害に対する意識については、以下の点を押さえておきましょう。
・お互いの人格を尊重し合うこと、つまり何人も性別によらずその人格全体と個性が尊重されるべきであること
・お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと、つまり職場において女性労働者も男性労働者も対等な働き手であること
・相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと
・女性を劣ったせいとして見る意識をなくすこと、つまり人の性別に基づき固定的な役割分担をさせることが不適切であること
国が掲げるセクハラ対策の内容とは
国は、事業主に対し、職場でセクハラ被害が発生しないよう次のような防止措置を講じることを義務付けています。
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(1)職部におけるセクシャルハラスメントの内容・セクシャルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
(2)セクシャルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)相談窓口をあらかじめ定めること
(4)相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること
3 職場におけるセクシャルハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
(5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること
(6)事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと
(7)事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと
(8)再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も同様)
4 1から3までの措置と合わせて講ずべき措置
(9)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
(10)相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

セクハラによってどのような責任が生じるか
セクハラ行為に対しては、法的責任が追及される可能性があります。
以下では、その追及される対象を加害者の場合・企業に分けて検討します。
加害者に問われる責任
まず、加害者に対して、セクハラの被害者は性的自己決定権などの人格権や、働きやすい職場環境の中で働く利益を侵害されたとして不法行為責任を追及することが考えられます。
また、実際の裁判例としてはあまり多くはありませんが、セクハラによって自らの名誉を毀損されたとして、名誉棄損による責任を追及することも考えられます。
企業に問われる責任
これに対して、セクハラの被害者や加害者を雇用する企業は、労働契約上の付随義務または不法行為法上の注意義務として、労働者に対し「働きやすい良好な職場環境を維持する義務(職場環境配慮義務)」を負っているとされています。そこで、セクハラが発生した場合には、この義務に違反したものとして、債務不履行ないし不法行為を理由に責任追及される可能性があります。
また、加害者のセクハラ行為は、「事業の執行につき」つまり、業務に付随して行われることもありえます。そのような場合には、使用者たる事業主には、使用者責任という民法上認められた特別な責任が追及されることもあります。
セクハラの被害者としては、セクハラ加害者・企業に対し、上記の責任として、損害賠償請求をすることも可能です。通院・休業等せざるを得なくなったという損害だけでなく、精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の支払義務が認められるケースもあります。
セクハラが裁判などで争点とされるようになった平成2年ころから、裁判で認められた慰謝料は概ね30万円程度から300万円程度の範囲に多く分布しているとされていますが、ひどいセクハラ被害の場合は500万円を超えるケースも見られます。
むろん、セクハラがあったからといって、精神的苦痛がなかったとされる場合には慰謝料支払義務を否定される場合もありますが、加害者だけではなく企業にもこのような責任が問われかねないということは理解しなければなりません。
相談を受ける側としてのセクハラ問題⑥
問題を解決するまでのステップ
セクハラが発生してしまったという相談があった場合には、以下の流れ・手順で事件解決まで進めていく必要があります。
1 被害者とされる者・相談者への意向確認
第一に、その被害者や相談者が、何を、どこまで求めているのか ということを確認する必要があります。
たとえば、加害者とされる相手に対し、具体的なアクションを求めていない場合もあるでしょうし、まずは相談を聞いて欲しいだけだというケースもあるでしょう。
話を聞くにあたって、具体的なアクションありきで対応してしまうと、相談をしている者の需要とかみ合わず、「これからは相談しづらい」と感じさせてしまうかもしれません。話を聞いたその場で評価してしまわずに、まずはその意向をくみ取ることに専念しましょう。
2 事実などの調査
相談に対し、門前払いはせずに、物証などがなくても時間をかけて丁寧に事実確認をするようにしましょう。
中には、セクハラ被害者とされる者が、加害者としていたはずの者にセクハラ被害があったとすれば考えにくいようなやり取りをしていた過去があるかもしれません。しかし、セクハラ被害者は職場での人間関係の中で行われるもので、被害者が加害者に迎合的な対応をとってしまうということもままあることです。
加害者から「被害者も嫌がっていなかった(自分は相手の意に反した言動はしていない)」などという反論が出されることもあるでしょう。しかし、最高裁での判例でも、被害者の対応として「著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも、職場の人間関係の悪化等を懸念して加害者に対する講義や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控えたりちゅうちょしたりすることが少なくない」として明確な拒否姿勢を示されていない場合でも、セクハラが成立しうることを認めています。
以上ことを十分に意識しながら、当事者の特性や、調査の対象・範囲、さらに方法にも注意し、相談内容事実について調査を進めます。
3 判断
調査の結果、セクハラの事実が認められるか否か判断します。
被害者が迎合的な態度をとっていたとしても、それだけでセクハラの事実がなかったことにはなりません。被害者が、迎合的にならざるを得なかった可能性や、その背景にも思いを致し、合理的に判断していく必要があります。
4 対処
セクハラの事実が認められるようであれば、当然対加害者に対し適正な措置を検討します。ただ、この時、「加害者」に対しは、適正な手続を踏み、重すぎない処分などの措置で臨まなければなりません。どのような行為が問題になるのかの具体例などを一覧にして作成し、周知しておくことも良いかもしれません。
また、被害者に対しても、適正な措置をしていること、あるいは進捗を知らせるなど、随時のフィードバックを欠かさないようにしましょう。
これに対し、もし、セクハラの事実が認められなかった場合はどうするべきでしょうか。セクハラというものは、明確な物証がないことも多く、加害者も事実を認めないこともありえます。また、被害者も全てを理路整然と説明できない場合もあるでしょう。
仮にセクハラ行為があったとは認定できなくても、その被害申告や相談の背景には、職場環境の問題点、たとえば人間関係のトラブルなどが隠れているケースもあります。セクハラ被害者・加害者に直ちに対処がしづらいケースでも、何か職場環境を変える必要性があるのではないかという観点で対応する必要はないか、慎重に考えてみてください。

相談・調査をしてからの対応の悩み
相談を受ける側として注意すべき点
被害者や加害者への調査の際には、以下の点に特に注意をしておきましょう。
調査義務
上記国が掲げるセクハラ対処の指針でも、以下の点を指摘しています。
①相談窓口の担当者、人事部門または専門の委員会等が、相談者及び行為者とされる者の双方から事実関係を確認すること、また相談者と行為者の間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること
②事実関係の確認が困難な場合等においては、男女雇用機会均等法に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること
被害者への調査についての注意点
まず、相談窓口で事実関係を確認するにあたり、二次被害の防止をすべきことや、被害者のメンタルヘルスへの配慮が必要です。
被害者は、セクハラ行為によって心理的に混乱が続いている場合や、人間不信になっている場合、さらには「自分にも落ち度があったのではないか」などと自信を失っている場合もあります。そのような中で、加害者たる行為者を庇うような発言や、被害者の落ち度を指摘するようなことは、二次被害に繋がりかねません。
被害者に精神的な不調が見られるような場合には、管理監督者や事業場内の産業保健スタッフに対応を依頼することも考えられます。
加害者とされる者への調査についての注意点
これに対し、加害者とされる者にも適切な対応が求められます。つまり、事情聴取の際には、セクハラ加害の事実が認められれば就業規則等の規定に従って処分される可能性もあることを説明した上で、弁明があればその内容を十分に聞き取ること、聴き取りについては複数名で行い、聞き取った内容や聞き取った手続などについてはきちんと記録をとっておくことです。
セクハラ加害があったことが認定できたからといって、このような丁寧な対応なしに手続を進め処分をしてしまうと、後日その処分自体の有効性を争われることもありえます。
調査の不備によって責任が追及されることも
上記のような注意点を意識せず、漫然と調査してしまったという場合、調査義務をきちんと果たしていなかったとして後日その調査主体たる企業側が訴えられ、責任が問われることもありえます。
実際、裁判例の中には、部下からのセクハラ苦情の申し出に対し、事情聴取を行わず証拠も集めないままに加害者を庇う発言を繰り返したという上司の言動に対し、調査義務の不作為があったとして、企業への慰謝料請求が認められたケースもあります。
企業内では解決できないと感じたら
外部機関への相談
もし、企業だけでは解決できないと感じた時には、外部機関の設置する相談窓口を利用するべき場合もあるでしょう。
たとえば、労働局雇用環境・均等部(室)などへの相談を促すことも考えられます。
公益通報者保護法との関係
職場内でのセクハラ加害について、事業主に通報すると、それは公益通報者保護法の適用がありえます。
公益通報者保護法の適用があるとされる通報内容は、単に違法な行為というだけではなく、法により直接的もしくは間接的に「刑罰」の対象とされる違法行為であることが必要ですので、例えば強制わいせつや強要罪等の成立が問われかねないセクハラ行為の場合は、これに当たる可能性が出てきます。
企業としても、相談や苦情申出を受けた内容が上記のような刑罰に繋がりかねない行為であった場合には、より一層の注意を要することは理解をする必要があるでしょう。
セクハラ対応はよりよい職場を作るためのもの
セクハラ対策は、それを実行することで、セクハラ被害者だけではなく職場にいる組織全体の関係者を助けるものです。
セクハラ加害に対して事後措置をすることは、気が重く、また事実認定や措置処分の決定など困難を伴いますが、よりよい環境づくりのために必須であり、今後二度と同じ被害を出さないためのものと考え、誠実に対応をしていきましょう。
また、セクハラだけでなく、ハラスメントの概念や法整備は日々進んでいくものです。過去の経験や国の出した指針、裁判例だけにとらわれず、日々研修・セミナー等で新たな知識を得ていく必要があります。
必要に応じて、労働局や弁護士事務所等の専門家に相談し、紛争や被害がなるべく拡大しないよう、常に努力をしていきましょう。
グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。








